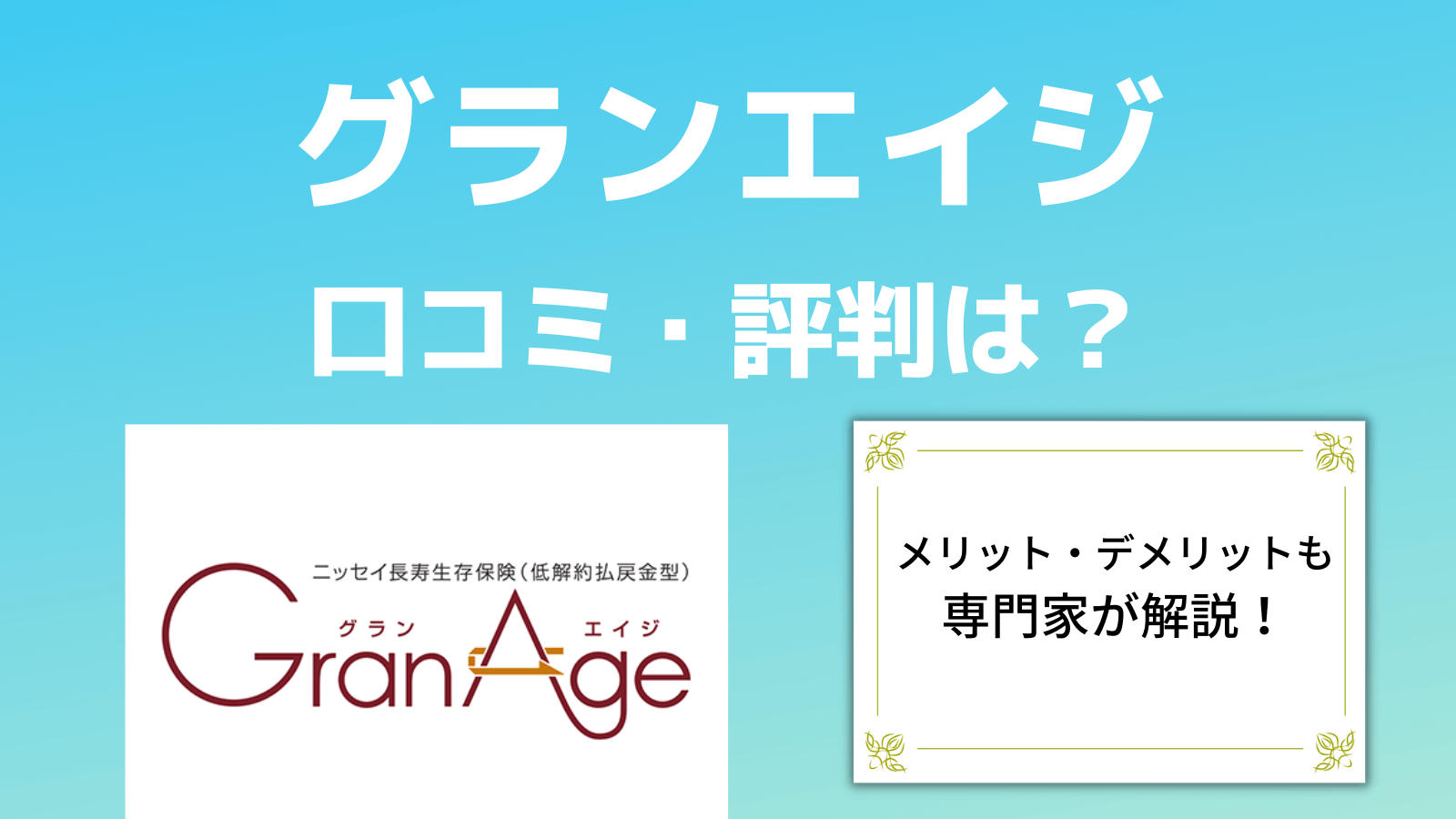日本生命が平成28年4月2日より発売している「グランエイジ」は、死亡時の保険金を抑えてその分生存保障をより重視したタイプの保険です。
日本人の平均寿命が伸び続けていることは多くの方が認識しており、実際に厚生労働省の「平成30年簡易生命表の概況」によると、平成30年の平均寿命は男性が81.25歳で女性が87.32歳となっています。
「長生きすること」は本来誰にとっても喜ばしい事ではありますが、そこに付随する経済的不安への備えは今や多くの人にとって欠かせないものとなっているのです。
そしてグランエイジであれば長生きするほど受け取れる保障が大きくなるため、長寿に対する経済的不安を解消してくれることが期待できる商品となっています。
そこでこの記事ではグランエイジの年金保険について、
- グランエイジの基本保障や特約の内容
- グランエイジの返礼率に関するシミュレーション
- グランエイジのメリットとデメリット
- グランエイジの対する口コミ・評判
- 第一生命のながいき物語やiDeCo、確定拠出年金といった類似金融商品との比較検討結果
以上の5点についてお話しします。
この記事を読めば、グランエイジの基本・特約保障内容や返戻率のシミュレーション、メリット・デメリット、口コミ・評判、他社商品との比較検討結果について知ることができます。
保険の契約に関するあなたの悩みを解決する記事になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
*「保険の営業マンに外貨建て保険を勧められたけど入るか迷っている」「色々調べたけど結局自分に向いている保険がわからない」という方は商品ランキングを確認後、下のリンクをクリックして外貨建て保険のプロ(FP)が揃った「マネーキャリア」で無料相談をすることをおすすめします。
外貨建て保険に限ったことではありませんが、保険営業マンに勧められたから加入するのは危険なのでおすすめしません。
「マネーキャリア」は強引な勧誘もなく、当サイトの管理人が自信を持っておすすめできる保険相談サービスの1つです。
保険相談は完全無料となっておりますので活用しないほうが損でしょう。(スマホ・パソコンでオンライン相談が可能)
※他にもほけんのぜんぶなどの保険相談サービスがありますが、オンライン相談に強いマネーキャリアをおすすめしています。

10年以上の長期で運用するなら、金融商品全体で見てもトップクラスの利率の高さでしょう
↓今すぐ外貨建て保険のおすすめランキングトップ3を知りたい、保険相談したい方はこちら↓
外貨建て保険おすすめランキング
第1位:メットライフ生命「ビーウィズユープラス2」:5.19%
→ビーウィズユープラス2が自分に向いているか相談する
第2位:マニュライフ生命「こだわり個人年金」:5.03%
→こだわり個人年金が自分に向いているか相談する
第3位:マニュライフ生命「未来につなげる終身保険」:4.96%
→未来につなげる終身保険が自分に向いているか相談する
内容をまとめると
- 日本生命のグランエイジは、低解約払戻金型長寿生存保険という生存保障を重視した年金保険。年金保障がメインで受け取り方式を3種類から選ぶことができる
- グランエイジのメリットは、節税効果がある、高いトンチン性で長寿への備えができる、健康告知が不要などがある
- 一方、インフレリスクに弱い、解約すると元本割れする可能性が高い、長生きしないと損になることもあるというデメリットもある
- グランエイジの口コミ・評判は「死亡保障はそこそこで年金保障が手厚いものを探していた自分にはぴったり」「告知なしで加入できるが良い」「年金だけでは不安な老後の生活資金に備えられる」など
- 第一生命のながいき物語と比較すると、返戻率にそこまでの差はないので、保険料負担綾契約開始年齢などご自身の状況でよりメリットが多い保険を選ぶべき
- 自分はグランエイジに加入した方が良いのか知りたいという方は保険のプロに無料相談するのがおすすめ
- 当サイトがおすすめしているのは筆者も使ったマネーキャリア
- 今ならスマホ1つで無料オンライン相談もできるので、この機会に保険の悩みを解決してみてはいかがでしょうか
目次
日本生命「グランエイジ」の評判・口コミは?
グランエイジのメリットは理解できても、本当にいい保険なのかまだ疑問が残る方は多いことでしょう。
そこで、ご検討中の方が一番気になる、実際の加入者の口コミ・評判をいくつかまとめてみました。
グランエイジの運用例、具体例に触れることで今後の資産運用のイメージを固めていきましょう。
実際の口コミや評判を紹介していきます。
日本生命の個人年金保険「グランエイジ」の評判・口コミの評価①
1つ目は日本生命の個人年金保険「グランエイジ」についての口コミをいただいた京都府のA・Kさん(51歳)の評価です。
「死亡保障はそこそこでいいので、年金という形で老後の生活を保障してくれる個人年金保険を探していました。これは保障がシンプルな分返戻率が高いので余計な保障で返戻率が下がるのが嫌だった私には最適な保険でしたね。」
保障がついている分返戻率が下がってしまうのが一般的ですが、日本生命のグランエイジ(ニッセイ長寿生存保険(低解約返戻金型))は、死亡保険金を最低限に抑えているためその分高い返戻率が期待できるのが強みです。口コミ提供ありがとうございました。
日本生命の個人年金保険「グランエイジ」の評判・口コミの評価②
2つ目の日本生命の個人年金保険「グランエイジ」の口コミは愛知県のH・Mさん(63歳)の評価です。
「返戻率の高さは言うまでもありません。円建てで約110%の返戻率なのでここまでの高い利率で運用できるのは驚きです。また、この年になると告知にひっかかる危険性が高いので告知無しで加入できるのも安心ですね。」
先程のシミュレーションでも返戻率がどのケースでも105%以上になるため、H・Mさんの述べている通り高い返戻率が期待できる個人年金保険です。また、無告知で加入できるというのも健康に不安が出てくるシニア向けならではの特徴と言えるでしょう。口コミ提供ありがとうございました。
日本生命の個人年金保険「グランエイジ」の評判・口コミの評価③
3つ目の日本生命の個人年金保険「グランエイジ」の口コミは東京都のI・Iさん(59歳)の評価です。
「長生きした時に生活資金が不足するというリスクにしっかり備えられる個人年金保険だなと感じています。これはトンチン年金というものですと日本生命の人に聞いて納得しました。細かいことですが、生命保険料控除やクレジットカード払いにできるので、節税にもなりますし助かります。」
長生きリスクに備える保険のため、長生きすればするほど高い返戻率の状態で年金を受け取ることができるトンチン性が高くなっています。口コミ提供ありがとうございました。
「口コミを見てもグランエイジが自分に合った保険なのかわからない...」という方は、保険の専門家に無料相談するのがおすすめです。
当サイトが激押ししているマネーキャリアというサービスは保険選びの際に役に立ったので公式ホームページだけでもチェックしてみてください。
*「保険の営業マンに外貨建て保険を勧められたけど入るか迷っている」「色々調べたけど結局自分に向いている保険がわからない」という方は商品ランキングを確認後、下のリンクをクリックして外貨建て保険のプロ(FP)が揃った「マネーキャリア」で無料相談をすることをおすすめします。
外貨建て保険に限ったことではありませんが、保険営業マンに勧められたから加入するのは危険なのでおすすめしません。
「マネーキャリア」は強引な勧誘もなく、当サイトの管理人が自信を持っておすすめできる保険相談サービスの1つです。
保険相談は完全無料となっておりますので活用しないほうが損でしょう。(スマホ・パソコンでオンライン相談が可能)
※他にもほけんのぜんぶなどの保険相談サービスがありますが、オンライン相談に強いマネーキャリアをおすすめしています。

10年以上の長期で運用するなら、金融商品全体で見てもトップクラスの利率の高さでしょう
↓今すぐ外貨建て保険のおすすめランキングトップ3を知りたい、保険相談したい方はこちら↓
外貨建て保険おすすめランキング
第1位:メットライフ生命「ビーウィズユープラス2」:5.19%
→ビーウィズユープラス2が自分に向いているか相談する
第2位:マニュライフ生命「こだわり個人年金」:5.03%
→こだわり個人年金が自分に向いているか相談する
第3位:マニュライフ生命「未来につなげる終身保険」:4.96%
→未来につなげる終身保険が自分に向いているか相談する
日本生命 グランエイジの保障内容を解説!トンチン年金としての利便性大
グランエイジは正式名称を「低解約払戻金型長寿生存保険」という、生存保障を重視した年金保険です。
- 基本情報
グランエイジの基本情報は下記の通りです。
| 保障種類 | 年金保障 |
| 契約指定通貨 | 円貨 |
| 契約年齢範囲 | 50歳~87歳 |
| 保険金額 | 払込保険料による |
| 保険料払込期間 | 全期払(男性:3年~30年・女性3年~35年※契約年齢によって異なる) |
| 保険料払込方法 | 月払・年払・前納 |
| 口座振替扱い・クレジットカード扱い | |
| 契約者貸付 | あり |
| 告知 | なし |
グランエイジはシニア向けの保険であり、健康告知なしで50歳以降からでも加入できるのが大きな特徴となっています。
また、死亡保険金は解約返戻金と同額になってしまう代わりに年金原資を大きくする生存保障重視の仕組みも大きなポイントです。
- 保険金や返戻金の受取方式
グランエイジの保険金は年金保障をメインとしており、死亡時は死亡払戻金として解約時の返戻金と同額のみしか受け取れない仕組みになっています。
年金保障の受取方式は5年保証期間付終身年金と10年確定年金の2種類に加えて、一括受取を選択することも可能です。
一括で受け取ればまとまった資金になりますし、別の方法で運用することも可能である一方、分割で受け取っていった方が最終的な累計受取年金額は基本的に大きくなります。
年金開始時のご自身の状況に応じて、様々な受取の選択肢をとることができるのです。
- 特約
グランエイジに付加できる特約は、下記の通りです。
| 個人年金保険料税制適格特約 | 払込保険料を個人年金保険料として所得控除をけられる特約 |
| 保険料口座振替扱特約 | 保険料の払込を口座振替でできる様になる特約 |
| 保険料クレジットカード扱特約 | 保険料の払込をクレジットカードでできる様になる特約 |
| 事業保険扱特約 | 付加することで事業保険扱いとできる特約 |
グランエイジの特約は、保障を充実させるというよりは保険料払込の手続き関係のオプションが中心です。
税制に関する特約はご自身の負担に直接関係してくるため、なるべくきちんと押さえておく必要があるでしょう。
「結局自分はグランエイジに加入した方がいいのかな?」という人は保険のプロに無料相談してみるのがおすすめです。
スマホ1つで無料オンライン相談が可能なので、ぜひお気軽に利用してみてください。
*「保険の営業マンに外貨建て保険を勧められたけど入るか迷っている」「色々調べたけど結局自分に向いている保険がわからない」という方は商品ランキングを確認後、下のリンクをクリックして外貨建て保険のプロ(FP)が揃った「マネーキャリア」で無料相談をすることをおすすめします。
外貨建て保険に限ったことではありませんが、保険営業マンに勧められたから加入するのは危険なのでおすすめしません。
「マネーキャリア」は強引な勧誘もなく、当サイトの管理人が自信を持っておすすめできる保険相談サービスの1つです。
保険相談は完全無料となっておりますので活用しないほうが損でしょう。(スマホ・パソコンでオンライン相談が可能)
※他にもほけんのぜんぶなどの保険相談サービスがありますが、オンライン相談に強いマネーキャリアをおすすめしています。

10年以上の長期で運用するなら、金融商品全体で見てもトップクラスの利率の高さでしょう
↓今すぐ外貨建て保険のおすすめランキングトップ3を知りたい、保険相談したい方はこちら↓
外貨建て保険おすすめランキング
第1位:メットライフ生命「ビーウィズユープラス2」:5.19%
→ビーウィズユープラス2が自分に向いているか相談する
第2位:マニュライフ生命「こだわり個人年金」:5.03%
→こだわり個人年金が自分に向いているか相談する
第3位:マニュライフ生命「未来につなげる終身保険」:4.96%
→未来につなげる終身保険が自分に向いているか相談する
グランエイジの返戻率、利率をシミュレーション!利回りの良さを評価
ここからは、グランエイジの返礼率をシミュレーションいたします。
<基本情報>
契約時年齢:50歳
保険料払込期間:20年 (70歳受取開始)
保険料払込方法:月払・口座振替扱
| 年金種類 | 10年 確定年金 |
10年 確定年金 |
10年 確定年金 |
10年 確定年金 |
5年保証期間 付終身年金 |
5年保証期間 付終身年金 |
| 性別 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 月額 払込保険料 |
23,424円 | 23,652円 | 47,946円 | 58,680円 | 50,790円 | 62,526円 |
| 総額 払込保険料 |
5,621,760円 | 5,676,480円 | 11,507,040円 | 14,083,200円 | 12,189,600円 | 15,006,240円 |
| 年間 受取年金額 |
600,000円 | 600,000円 | 1,271,000円 | 1,540,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
| 累計 受取年金額 |
6,000,000円 | 6,000,000円 | 12,710,000円 | 15,400,000円 | 18,000,000円 (99歳時点) |
18,000,000円 (99歳時点) |
| 返戻率 | 106.7% | 105.7% | 110.5% | 109.4% | 147.7% | 120.0% |
参考:日本生命HP
いずれも105%を上回る高い返戻率となりました。
終身年金を選択するともし早期に亡くなってしまえば受取額が払込保険料を下回ることもある一方、ご覧の通り長生きすればそれだけ高い返戻金を受け取ることができます。
このいわゆるトンチン性の高さが、グランエイジを選択するうえでの最大のメリットと言えるでしょう。
↓↓↓サイト管理人が利用してから激押ししている保険無料相談サービスはこちら↓↓↓

グランエイジのメリット・デメリットをわかりやすく解説
ここまでは、グランエイジの基本保障や特約内容、返戻金のシミュレーションについてお伝えしてきました。
ここからはより具体的に、グランエイジのメリットやデメリットを
- (メリット)生命保険料控除によって節税が期待できる点
- (メリット)高いトンチン性で長寿への備えができる点
- (メリット)健康告知が不要な点
- (デメリット)インフレリスクへの弱さ
- (デメリット)解約時の元本割れリスク
- (デメリット)満足のいく保障には長期間の積立が必要な点
上記の通り3点ずつに整理して説明いたします。
メリット➀:生命保険料控除が可能!確定申告や年末調整で申告しよう
個人年金保険料を支払った場合、支払った保険料額に応じて翌年の所得税や住民税の控除を受けることができることが、大きなメリットの一つです。
通常であれば生命保険料控除の枠内で、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合は個人年金保険料控除の枠内で控除がされます。
つまり、特約付加すれば生命保険料控除の枠を潰さずに控除を受けられるということなのです。
所得税と住民税における控除金額を以下にまとめています。
| 既払込保険料 | 控除額 | |
| 所得税 | 20,000円以下 | 既払込保険料全額 |
| 20,001円~40,000円 | (支払保険料等×1/2)+10,000円 | |
| 40,001円~80,000円 | (支払保険料等×1/4 )+20,000円 | |
| 80,001円以上 | 一律40,000円 | |
| 住民税 | 12,000円以下 | 既払込保険料全額 |
| 12,001円~32,000円 | (支払保険料等×1/2)+6,000円 | |
| 32,001円~56,000円 | (支払保険料等×1/4 )+14,000円 | |
| 56,001円以上 | 一律28,000円 |
所得税率は年収によって変化し、住民税率は10%で固定です。
たとえば仮に所得税率20%・住民税率10%で年間80,001円以上の保険料を支払ったとすると、
所得税:40,000円(控除額)×20%(税率)=8,000円
住民税:28,000円(控除額)×10%(税率)=2,800円
合計 :8,000円+2,800円=10,800円
下記の通り年間で10,800円の節税になるのです。
単年ではあまり大したことではないと思うかもしれません。
けれども保険料払込期間25年であれば合計270,000円、保険料払込期間30年であれば合計324,000円もの非常に大きな節税につながるのです。
受取年金の充実には長期間の払込が一定必要であるグランエイジにおいて、上記のような節税効果は保障の一部と言っても過言ではありません。
確定申告や年末調整時には忘れずに払込保険料の申告をしましょう。
メリット➁:高いトンチン性!終身保障と高返戻率で長生きリスクへ準備
年金2000万円問題が大きくとりあげられて以降、長く生きていくことに対する私たちの不安は非常に大きくなっています。
終身年金を選択すれば一生涯の年金保障を受けることができ、長生きすればするほど高い返戻率が期待できるようになる、いわゆるトンチン性の高さはグランエイジを利用する大きなメリットなのです。
円金利が非常に低くなっている現代において、105%を超える返戻率を実現している円建て年金保険は、グランエイジ以外にはそう多くありません。
国民年金や厚生年金の保障にプラスしてグランエイジの終身年金を利用することで通常の生活には十分な資金を確保することができ、安心して人生100年時代を生き抜いていくことができるでしょう。
メリット➂:健康告知や医師の審査が不要
グランエイジは通常生命保険等の契約をする際に必要な健康告知や医師の審査なく契約することができるため、健康状態に不安のある方でも安心して契約すできる保険です。
そもそも健康告知が必要となるのは、保険制度を健全かつ公平に保つためであると考えられます。
健康状態に不安があるということは保険を請求する可能性が高いということであり、健康告知を不要にして請求可能性が高い人が契約者に増えすぎると、
- 保険金支払額が高騰し、通常の保険料では支払いきれなくなる
- 健康な人(保険金受け取り可能性が低い人)にとって不公平感が高くなる
上記のような問題が発生するのです。
そしてこの状態が進行すると以下のような事態にまで発展し、
- 保険金の高騰に対応するため、保険料が異常に高くなる
- 病気になってから契約し、契約後に発病したとする虚偽請求行為(アフターロス)を誘発する
保険制度の維持が困難になってしまいます。
しかしグランエイジは長期的に契約をして払込保険料を積み立てていくことで初めて契約者のにメリットがある商品ですから、健康告知を不要としても問題が無いのでしょう。
また、グランエイジは年金の受取方法も選択できますから、年金受取時に健康に不安を感じるのであれば確定年金や一括受取を選択することで、必要以上の損失を回避することもできます。
デメリット➀:インフレリスクに弱い!長期的に資産の流動性を失う
グランエイジの年金受取額は、契約時に確定します。
契約時に年金額が決定するということは、長い保険料払込期間中に想定以上のインフレが進んだ場合に受取額が目減りしてしまい、大きく損失を被る可能性があるということなのです。
もっとも、グランエイジは月払や年払で分割して保険料を払っていく分インフレリスクは軽減されていますし、比較的高い返戻率が期待できます。
よほどのインフレにならない限りは問題とはならないとは思われますが、十分に注意しておく必要はあるでしょう。
また、グランエイジのように長期間保険料を払い込み続けるということは、一定の資産が長期間に渡って流動性を失ってしまうことにもつながります。
これらのことを総合して考えると、保険料の設定は無理のない範囲で行い、長期的展望を持って契約をすることが大切でしょう。
デメリット➁:保険料払込期間中に解約すると解約返戻金が必ず元本割れする
グランエイジの解約返戻金は低く設定されているため、保険料払込期間中に解約するといずれの時期であっても元本割れします。
また、保険機能は年金保障のみであるため、保険料払込期間中に死亡した場合は死亡返戻金として解約返戻金請求時と同額しか受け取ることができません。
そのため、払込期間満了まで契約して年金を受取らなくては、必ず損失を被ってしまうのです。
また、グランエイジの契約は早くても50歳からのスタートですから、受取年金額をそれなりに充実させようとしたら月々の保険料も比較的高額になりやすいという特徴があります。
けれどもそういった仕組みをとっているがために、その分高い返戻率を実現できているという訳です。
契約を検討する場合には払込期間まで払い込むことを前提として計画を立てる必要があるでしょう。
デメリット➂:返戻率が高まるまでに一定の保険料積立期間が必要!損益分岐点をシミュレーション
グランエイジは終身年金を選択することで長生きすればするほど総年金受取額が大きくなり得をする保険商品ですが、逆の言い方をすればそれは長く生きなければ損になるということでもあります。
具体的に検証するために、先ほど返戻率のシミュレーションで用いた5年保証期間付終身年金の場合で更に年齢を細かくシミュレーションし、損益分岐点を確認してみましょう。
<基本情報>
年金種類:5年保証期間付終身年金
年金受取開始年齢:70歳
月払保険料額:(男性)50,790円・(女性)62,526円
年間受取年金額:600,000円
総額払込保険料:(男性)12,189,600円・(女性)15,006,240円
| 累計年金受取額 | 返戻率 (男性) |
返戻率 (女性) |
|
| 74歳 | 3,000,000円 | 24.6% | 20.0% |
| 79歳 | 6,000,000円 | 49.2% | 40.0% |
| 84歳 | 9,000,000円 | 73.8% | 60.0% |
| 89歳 | 12,000,000円 | 98.4% | 80.0% |
| 90歳 | 12,600,000円 | 103.3% | 84.6% |
| 93歳 | 14,400,000円 | 118.1% | 96.0% |
| 94歳 | 15,000,000円 | 123.1% | 99.9% |
| 95歳 | 15,600,000円 | 128.0% | 104.0% |
| 99歳 | 18,000,000円 | 147.7% | 120.0% |
上記の通り男性であれば90歳、女性であれば94歳まで年金を受取り続けることで返戻率100%を達成することができました。
反対にもし70代で亡くなられてしまうと、払い込んだ保険料の内半分も回収できないことになります。その損失は、場合によっては1,000万円近くになることも考えられるのです。
ただしグランエイジには確定年金や一括受取という選択肢も残されていますので、どのような健康状態であっても保険料払込満了後の利益を確保することは可能ではあります。
メリット・デメリットを見てもグランエイジに入るべきなのか悩んでいるという人は、保険のプロに無料相談してみるのが一番良いと思います。
家族構成や年収などからあなたにどんな保険がピッタリなのか診断してくれます。
スマホかパソコンで無料オンライン相談ができるので、気になる人は以下のボタンから公式サイトをチェックしてみてください。
グランエイジと第一生命の「ながいき物語」のシミュレーションを比較
ここでは、日本生命「グランエイジ」と第一生命「ながいき物語」やiDeCo、確定拠出年金や外貨建て保険との比較検討を行います。
まずは日本生命「グランエイジ」と類似点の多い商品である第一生命「ながいき物語」とを比較してみましょう。
| 日本生命「グランエイジ」 | 第一生命「ながいき物語」 | |
| 保険種類 | 低解約払戻金型長寿生存保険 | 生存保障重視型個人年金保険 |
| 契約 指定通貨 |
円貨 | 円貨 |
| 契約年齢 範囲 |
50歳~87歳 | 50歳〜80歳 |
| 保険料 受取方法 |
年金保障 (5年保証期間付終身年金・10年確定年金) |
年金保障 (10年保証期間付終身年金・5、10、15年確定年金) |
| 保険料 払込方法 |
月払・年払・前納 | 月払・年払 |
| 特徴 その他 |
返戻率が個人年金保険としては高い 解約返戻金が低い 死亡保障が無い |
返戻率が個人年金保険としては高い 解約返戻金が低い 死亡保障が無い |
両者ともに生存保障に重点を置いた個人年金保険であり、解約返戻金が低く設定されている点や死亡保障がない代わりに年金原資が大きくなる点など、非常によく似た性格の保険商品です。
それぞれの商品に関する受取シミュレーションを、以下の通り終身年金で比較してみます。
| グランエイジ | ながいき物語 | |||
| 年金種類 | 5年保証期間 付終身年金 |
5年保証期間 付終身年金 |
10年保証期間 付終身年金 |
10年保証期間 付終身年金 |
| 契約時年齢 | 50歳 | 50歳 | 55歳 | 55歳 |
| 年金 受取開始年齢 |
70歳 | 70歳 | 70歳 | 70歳 |
| 性別 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 月額 払込保険料 |
50,790円 | 62,526円 | 54,000円 | 54,000円 |
| 累計 払込保険料(A) |
12,189,600円 | 15,006,240円 | 9,720,000円 | 9,720,000円 |
| 年間 年金受取額 |
600,000円 | 600,000円 | 511,100円 | 410,800円 |
| 累計年金受取額 (99歳時点)(B) |
18,000,000円 | 18,000,000円 | 15,333,000円 | 12,324,000円 |
| 返戻率 | 147.7% | 120.0% | 157.7% | 127.0% |
| (B)-(A) | 5,810,400円 | 2,993,760円 | 5,613,000円 | 2,604,000円 |
比較すると、ながいき物語の方が99歳時点での返戻率は高いと言えます。
ただし、「累計年金受取額-累計払込保険料(上表で一番下 (B)- (A)の欄)」、つまり「純粋にいくらの利益を得たか」で比較をすると、99歳時点でそれほどの金額差はありませんでした。
むしろ上の表であれば年間の年金受取額はグランエイジの方が大きいため、長生きをしていけばグランエイジの方がお得になっていくとも読み取れます。
両者に決定的な差があるとは言えない以上、保険料の負担可能額や契約開始年齢などご自身独自の条件によって両者を比較し、よりメリットが大きい商品を選択するべきでしょう。
参考:iDeCoや確定拠出年金の違いとは?グランエイジ(個人年金保険)にメリットはある?
ここからは、個人年金保険と類似した制度であるiDeCoや確定拠出年金との比較を行います。
まず確定拠出年金とは、公的年金に上乗せをして老後資金の積み立てを行う制度のことです。
確定拠出年金には企業型と個人型があり、個人型の確定拠出年金のことを特にiDeCo(イデコ) と呼びます。
それぞれの特徴を下記の通り簡単にまとめました。
| 個人年金保険 | 確定拠出年金 | ||
| 企業型 | 個人型(iDeCo) | ||
| 運営窓口 | 各金融機関 | 各企業 | 各金融機関 |
| 加入可能者 | 条件を満たせば誰でも可 | 条件を満たした会社員のみ | 条件を満たせば誰でも可 |
| 掛金 | 契約時確定(原則変更不可) | 原則変更可能 | |
| 年金額 | 契約時確定 | 運用結果により変動 | |
| 中途解約 | 可能 | 原則不可 | |
| 運用方針 | 保険会社が運用 基本利率は契約時に確定 |
企業が選んだ金融機関の運用商品から自ら選択し運用 | 自分で選んだ金融機関の運用商品から自ら選択し運用 |
| 税制 (積立時) |
下記の生命保険料控除あり 所得税:最大40,000円 住民税:最大28,000円 |
小規模企業共済等掛金控除にて、全額控除 | |
| 税制 (運用時) |
なし | 現状では非課税 (特別法人税が2020年3月末まで暫定的に凍結中) |
|
| 税制 (受取時) |
一時金:一時所得 年金 :雑所得 |
一時金:退職所得控除 年金 :雑所得として公的年金控除 |
|
- 運用面
個人年金保険もiDeCoを含む確定拠出年金も老後資金の準備という点では共通しているものの、運用方針やスタンスに違いがあります。
個人年金保険は年金額が確定していて安心感がある一方、確定拠出年金は年金額をより増やせる可能性はありますが年金額の保証がされていない点は注意が必要です。
- 税制面
税制面では、確定拠出年金やiDeCoは非常に優遇されています。
掛け金負担時には全額控除され、年金受取時には一時金での一括受取時は退職所得控除、年金として分割受取時は雑所得として公的年金控除されるのです。
また、運用時には本来特別法人税が課されることとなっているのですが、バブル崩壊をきっかけとして企業年金の運用状況が悪くなったために、平成11年度から凍結されて課税停止状態が続いています。
凍結は毎回延長され続け、現在では少なくとも2020年3月末までの凍結が確定しているのです。
元々企業の運用実績が芳しくないがために凍結されたわけですから、史上まれにみる低金利と言われている今のタイミングで凍結が解除されるとは考えにくく、今後も非課税が続くと考えるのが自然ではないでしょうか。
また、確定拠出年金(iDeCoを含む)には掛け金の上限が存在することも認識しておく必要があります。
より大きな額を積み立てたいと考えるのであれば確定拠出年金に加えて個人年金保険も併用するなど、両者の特徴を踏まえた使い分けや組み合わせを行うようにしましょう。
外貨建て保険ならコスパの良い資産形成が可能!?外貨建て保険のメリットとは?
グランエイジは、円建ての個人年金保険としては返戻率がとても高い商品です。
しかし、拠出した積立金を運用し、老後の生活をより豊かにするべく年金額を増やそうと考えるのであれば、高利率な外貨建て保険の活用も視野に入れるべきでしょう。
円は現在、非常に低金利な状況が続いており、円建て商品では大きなリターンはどうしても期待しにくい状況となっています。
一方、外貨建て保険は外貨の高利率で運用することができる商品であり、高い返戻率はもちろん保険金に関して元本保証がされているものも多くあるのです。
また、保険金を外貨で受け取れる場合は一度受取っておいて為替状況を見て円換金するなど、資産運用方針により一層の幅も生まれてきます。
外貨で運用するうえでの注意点は当然あるものの、不確定なことが多い老後をより安心して過ごしたいと考えるのであれば、外貨建て保険は必ず検討すべき選択肢であると言えるでしょう。
↓↓↓サイト管理人が利用してから激押ししている保険無料相談サービスはこちら↓↓↓

まとめ:グランエイジを老後の資産形成や長生きリスクへの備えに活用!
この記事では、日本生命「グランエイジ」の年金保険について
- グランエイジの基本保障や特約障内容
- グランエイジの返戻金シミュレーション
- グランエイジ年金保険のメリットやデメリット
- グランエイジの評判や口コミ
- グランエイジと類似金融商品との比較
上記についてお話ししてきました。
グランエイジにおけるポイントとしては、
- 比較的高い返戻率で長生きへの不安が大きく解消される点
- 老後資産の準備に出遅れた方や健康に不安のある方でも問題なく利用できる点
以上であるといえるのではないでしょうか。
長生きは本来喜ばしいことのはずなのに、長生きすればするほど心配なことも増えていってしまうのが現状です。
けれどもグランエイジを利用すれば不確定要素の多い長生きリスクへの備えができ、いくつになっても安心して生活していける、老後人生のしっかりとした土台を築くことができるでしょう。
もし、グランエイジについてより詳細な話が聞きたい、他の個人年金保険と比較してみたいなどのご要望がございましたら、無料の「保険相談サービス」を利用することをおすすめします。
個人年金保険は、不確定な要素が多い老後への備えとして長期間の負担を強いられる性質の保険商品であり、インターネットの情報だけではなかなか心配が解消されないということもあります。
そんな場合は、マネーキャリアという保険のプロ(FP)に無料相談できるサービスがございますので、こちらでライフプランの相談も含めた保険の相談をすることをおすすめします。
保険相談の担当者は全てベテランのスタッフですので、難しく心配事の多い個人年金保険でもわかりやすく説明してもらえ、自分に合った保険を納得して選べるでしょう。
↓↓↓サイト管理人が利用してから激押ししている保険無料相談サービスはこちら↓↓↓

▼おすすめの外貨建て保険は以下のページで解説しています!